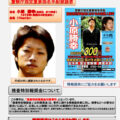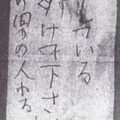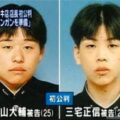今回はイメージ画像が怖すぎることで有名な岡山地底湖行方不明事件の謎を考察するよ
うわぁ…。ここに落ちちゃったってことですよね?
そうなんだ。男子大学生がここで行方不明になってしまって、そのまま見つかっていないんだ。被害者のNさんは一緒に来たメンバーによって○害されたなどという説も囁かれてるよ。
えっ!どういうことですか?!他⚫︎ということですか!?
では事故の概要から説明していくよ。
日本の未解決事件: 闇に消えた真実、謎の事件の真相に迫る 事件考察解明シリーズ
目次
事件概要
この事故が発生したのは2008年1月5日、岡山県新見市にある日咩坂鐘乳穴(ひめさかかなちあな)の地底湖で、当時21歳の大学生だったNさんが行方不明になったんだ。
中国・四国の学生ケイバーを中心として開催されていたケイビング合同合宿での出来事で、
Nさんは高知大学学術探検部に所属しており、このケイビング合同合宿に参加していたんだ。
※ケイビング・・・趣味やスポーツとして洞窟に入る探検活動のこと
この事件のケイビングではNさん含め計15名が参加した。
想像以上に大人数で行ってたんですね。4、5人かと思いました。
でも事故前日の夜、班編成変更により、日咩坂鐘乳穴には5名で入洞しているようなんだ。
他のメンバーは違うルートになったみたい。
過去2回行われた合宿では、日咩坂鐘乳穴には合計4回入洞が行われており、
地底湖畔に到着すると泳ぎに自信のない者以外は、一度は地底湖を横断して、
対岸の鐘乳穴最奥部の壁に到達することが慣例となっていたんだ。
危険な慣例ですね。ケイビング界隈ではそうでもないのかな。
今回の事件でもその慣例をみな意識していたようだ。ただ慣例といえど無理やりに泳がせるようなことはNさんは泳ぐかどうか迷っていたが結局泳ぐことに決めたそうなんだ。
メンバーが数十秒間Nさんから目を離したのちに対岸を見たとき、
Nさんの姿は確認できなかった。
断続的に「Nくーん!」「早く戻ってこーい!」などと呼び掛けていたが応答はなく、
水音や反響で聞えていないと考えた班員が「おーい」と呼び掛けると、初めて「おーい」との声がNからしかし4度目に「おーい」との呼び掛けを行ったがNからの応答はなかった。
応答が途絶えたため、班員らはここでNさんに不測の事態が発生したと考え、各自大声で呼び掛けたが応答はなかった。
この時、洞壁や水面にはNさんのライトの反射は見えず、湖面にも波紋はなかった。
Oさんが左壁面沿いに5、6メートル泳ぎ出て、死角のない位置から湖面全体を確認したが、Nさんの姿はなかった。
午後2時50分に出洞を開始し、
出洞するまでの間にOさんとFさんが通報について検討を行い、警察と消防に通報する必要があるとの結論に達した。
徹夜で捜索を行ったが、捜索隊の体力の消耗も激しく、6日午前8時に一旦中断し、7日午前9時から再開することとした。
捜索隊が入洞してのち、連絡員1人を神社に残したほかは合宿参加者は全員宿所に戻っていたが、
6日朝の起床後に日咩坂鐘乳穴へ向い、出洞してきた捜索隊からDさんら3人が状況説明を受けた。
その話から、捜索は水中のみであり支洞部分は行っていないことを知り、
二次災害のおそれの少ないDさんら3名が捜索を行うことを提案し、警察も了承した。
・3名は午前11時に入洞したが、第二ラダーポイントで残置されていると考えていた補助ロープを発見で時に出洞した。
その後、現地に駆け付けた高知大学学術探検部OBの1名を加えて、
警察に連絡の上午後6時20分に再び入洞、2人ずつに分かれてそれぞれ支洞と地底湖の捜索を行ったがNさんが見つかることはなかった
やはり湖に沈んでしまって見つからなかったように思えますね。
場所も普通の湖と違って捜索しづらいでしょうし。
それに湖は乳白色に濁っていて全く下が見えなかったらしいよ。
じゃあ次はこの事件に囁かれている不可解な点を話していくよ。
岡山大学生地底湖行方不明事故7つの謎
1.Nさんだけが地底湖を真冬に服を着たまま25メートル泳ぐのは不可解
先ほども言ったように地底湖遊泳は慣例になっていたんだ。
横断途中に危険を感じた者は多かったが、経験談としては達成感を強調したり、
武勇伝として語られることも多かったため、危険性の認識には差があった。
最奥での余興イベントと考えている者もいたという。
大学生ですし想像できます。でもこの辺りは批判されそうなポイントですね。
2.毎年恒例で届ける必要性を分かっていたはずなのに入洞届を出していない
,入洞届って何ですか?許可がいるんですか?
入洞届は、洞内での事故など不測の事態が発生した場合に備えて役所に提出するものだよ。
これを届けていなかったことからこのケイビングのメンバーが不真面目なのではないかというイメージを持つ人がいるみたいだね。
それを聞くとそんなイメージを私も持ってしまいますね。
3.「タッチした」という声が聞こえたとメンバーは言うが本当に声が聞こえたのか?
警察が捜索に入ると地底湖の水により声がかき消されたそうなんだ。
そのため25メートル先での声が聞こえたとは考えにくいというものだね
それは、他のメンバーの証言が嘘だったということですか?
そう考える人がいるみたいだね。
4.溺れた可能性と言って警察に届け出ているが溺れた姿を見た人はいない。
仮に溺れたのだとしても助けを呼ぶ声は誰も聞いていないのはおかしいというものだよ。
むむ。まさかメンバーが何か隠している?
5.入洞した際メンバーは5人とされているが4人になったり3人になったりニュースによって人数が変わっている
入洞した際メンバーは5人とされているが4人になったり3人になったりニュースによって人数が変わっていることだ
事件の関係者の人数が変わるのはもはやあるあるですね。きっとこれは闇ではないですね。
6.溺れた可能性があるにも関わらず残りの4人全員で現場から立ち去っている
溺れた可能性があるにも関わらず残りの4人全員で現場から立ち去り、
地底湖から挙げる為に必要なロープなど持って出ている説だね
まだNさんが助かる可能性があるのにロープを持って出た?まさか…。
7.探検サークルのHP上で部長と副部長の名前が事故後削除
これは!完全に闇ですね!恐らく組織の子供が関係してたからですね。
不可解な点を聞くとこの事件が闇深いと言われるのもわかります。
では、ここからは不可解な点を私が考察していくよ。
幽理の考察
1,Nさんだけが地底湖を泳いだ謎
最初の謎、入洞したメンバーは5人、Nさんだけが地底湖を泳いでおり、真冬に服を着たまま25ⅿ泳
これは事故報告書を読めばわかる
実はNさんとKさん(横断経験なし)の2人が地底湖横断に興味を示したことが報告書に書かれている。
まずKさんが横断を試み、2、3 メートル程進んだが足がつかなくなったためその地点で引き返し
Kさんは泳げなかったようだ。
Kが横断を断念した後は他に横断を試みる者はなかった。
Kさんが出洞を提案すると、Nさんは「浮き輪やフィンがあればいいのにな」「ここは無理そうです
心残りがあるものの、他の班員が泳ごうとしないため決心がつかない様子であったという。
その様子を見た他の班員から、日咩坂鐘乳穴に入洞する機会は少ないため、
心残りがあるのなら行ったらどうか、という趣旨の発言があったが、Nは返答しなかった。
その後、Oも出洞を提案したためNさん以外の班員は出洞を開始しようとしていたが、Nさんはまだ
の班員を誘うような発言をした。
班員は自分は横断を行わないが、「行きたいと思うのであれば行った方が良いのではないか」とい
る。この返答の後、Nは数秒間湖面を見つめていたが、無言のまま地底湖中央を対岸へ向って泳ぎ始め
Oは照射距離の長いライトを点燈して、泳ぐNさんのヘルメット附近を照らし、他の班員も泳ぐNを見守った。
無理やり湖に落とされたわけではなかったのですね。
「岡山地底湖事件の闇」と概要だけ聞けば色々と想像が膨らんでしまいましたが、ここまでの情報だけでかなり印象が変わってくきますね。
想像するに、Nさんは、時間をかけて地底湖まで辿り着き慣例となっている地底湖横断をする機会が
Kさんも諦めて他のメンバーも泳ごうとはしないもどかしい気持ちだったんじゃないかな。
イジメや悪ふざけで無理やり地底湖に落としたりしたなど言っている人もいるが報告書だと全く違
もう一つ調べていてわかったのはこの地底湖まで辿り着くまでにほぼ水に使っているところを通る
全員服はびしょ濡れの状態だったということだ
真冬だから25メートルの湖を泳ごうとするわけがないと思う人も多いが、
地底湖に着いたメンバーにとって真冬であっても服が濡れるということは気になる要素ではないと
報告書内にも他の4人も全身が濡れていたと書いてあったよ。
さらにNさんはこの合宿までに、確認されているだけで24回の入洞経験があり(日咩坂鐘乳穴は
海水でマスクやシュノーケル、フィン及びウェットスーツを着用して2時間以上の突き漁を行った経
、海水でも淡水プールでも、100メートルを余裕を持って泳ぎ切るだけの泳力も有していたんだ。
Nさんの発言の「浮き輪やフィンがあればいいのにな」もフィンを使用したことがなければ言わない
更に高知県須崎市の樽の滝の滝壺で、事故時同様のアンダーウェアとつなぎで遊泳したことも3回ある。
この情報から事故当時の服装のイメージも変わったね
私服で湖を泳いだのではないかというイメージを持たれた方もいると思うが、
アンダーウェアとおそらく探検用のつなぎで泳いでいるんだ。
最初は何となく私服の大学生を想像していました。でもいかにNさんがタフでも経験したことない環境での泳ぎだとトラブルが起きる可能性がありますね。
Nさんは着衣水泳の講習等を受けたことはなかったほか、冬季に保温性のある装備なしで遊泳した
また、樽の滝での遊泳はいずれも5月から6月で、2008年6月の滝壺の水温は約16度だった。
そのほか、夜間や洞内での遊泳経験もこれまでになかったと報告書には書かれている。
むしろ泳ぎが得意な人の方がこのような事故は起きそうだね。
最初は泳ごうとしたけど足がつかなかったため断念したKさんは助かっているしね。
2,入洞届を出していない謎
次は毎年恒例で届ける必要性を分かっていたはずなのに入洞届を出していない謎を考察するよ。
届け出ると何か不都合な、真実が隠されているのでは…
洞窟に入洞する場合は、教育委員会生涯学習課への入洞届、入洞者名簿、連絡先、緊急時の連絡
任意で求められていた。
過去に2回行われた冬季阿哲台合宿ではこれらの提出は行わなかったが、生涯学習課へ入洞日程の
その際に計画書の提出も求められなかったとされる。
また、入洞前と出洞後には、日咩坂鐘乳穴神社の宮司に口頭報告を行っていた。
ただし事故が起ったこの年の合宿では、Dは役所が仕事納めをしていると考えて電話連絡を行ってい
また、2日に入洞した班は宮司への口頭報告を行っていたものの、事故当日の5日に入洞した班は、
入洞時に宮司が不在だったため、こちらへの口頭報告も行わなかった。
よくこのサークルのメンバーの素行や入洞届を出していないことを取り上げられているが、一応は任意とのことだった。
生涯学習課へ入洞日程の電話連絡も行っているため毎回誰にも連絡せずに入洞していたわけではな
もちろん安全に配慮して全ての届け出を任意とはいえ提出するべきという考え方も理解できるが、
この点もこの事故のイメージを変える情報だと感じたね。
しかしDさんは役所が仕事納めをしていると考えて電話連絡を行っていなかったという点はよくなか
事故当日は1月5日なので当日に電話連絡するのは計画性のなさを感じてしまう。
事故の起きた日は入洞時に宮司が不在だったため口頭報告も行っていなかったということなので、
結果的に普段から勝手に入洞していると思われることになってしまったのでしょう。
不真面目だったから届け出なかったわけではないのですね。年始だから気をつかったんですね。入洞届の謎は解けました。
3,「タッチした」という声の謎
次は「タッチした」という声が聞こえたとメンバーは言うが警察が捜索に入ると地底湖の水により声がかき消され25ⅿ先での声が聞こえたとは考えにくい、という謎を考察するよ。
まずウィキペディア内や当時の記事などで「タッチした」という声が聞こえたという記述を見つけることができなかった。
よくあるこの事故のまとめ記事などで下記のようなことを散見する。
地底湖で飲み会をし酔った勢いで地底湖の奥の壁まで泳いで
「タッチ」と言って戻ってくるという伝統があり、Nさんが地底湖を泳ぎ、奧の壁に到達して「タッチ」と
叫んだところまではメンバーが確認しているものの、その後、姿も声も見えなくなってしまった。
しかし、水面で暴れるなど溺れた様子もなく、助けを呼ぶ声も無かったのはおかしいのでは?という説だ。
この説明を最初に聞くと怪しさ満点ですね。
報告書の一部を見てみよう。
対岸に到着したNは片手を上げて合図を送るような動きを見せたが声は聞えず、
班員も「どう?」「大丈夫?」などの声を送ったが、返答や合図はなく、声は聞えていない様子であった。
・その後、対岸の岩に腰掛け、足を水につけて休んでいるようなNの姿をFが目撃している。
また、OとFが、水から完全に上がって立ち上り、周囲を観察するようなNの姿を確認した。
・その後、O、F、Kは、Nが戻り次第出洞するため、数十秒間Nから目を離していた。
次にOとFが対岸を見たとき、Nの姿は確認できなかった。
OとFは、こちらから死角となっている左壁に沿って戻ってくる途中であると思い、声で呼び掛けたが返答はなかった。見ると、右壁の天井附近にNのライトの明かりが当っているのが確認された。
このときのライトの動きはゆっくりとしており、泳いでいるときのような激しいものではなかった。
Oはライトの動きから、Nが左壁に摑まって右壁を観察しているものと思い、早く帰ってくるよう呼び掛けたが応答はなかった。
その後、天井に当っていたライトは移動し、確認できない時間が長くなった。
あれ?タッチしたって声聞いてなさそうですね。
ここから察するに、対岸に着いた人はタッチしたと叫ぶが聞こえない、こちらの声も聞こえないとメンバーも感じていたということがわかる。
ただ横断を成功させたメンバーが他のメンバーにこの慣例を話す際に「タッチ」と叫んだことを伝えて、
皆が聞こえはしないが対岸に着いたら「タッチ」と叫ぶものだと思い込んでいた可能性があるね。
仮に「タッチした」という声が聞こえたとメンバーが警察に言ったことが本当だとしたら、
「タッチした」ということが慣例であり対岸に到着したNは片手を上げて合図を送るような動きを
当然「タッチした」と言ったのだろうと思って警察に曖昧な情報を伝えてしまったのかもしれない
正直タッチしたと言ったかどうかはあまり重要ではなさそうなので仕方ないと思います。
戻ってくる途中に行方不明になっているのは明白ですもんね。
4.溺れた姿を見た人はいない謎
次は4.溺れた可能性と言って警察に届け出ているが溺れた姿を見た人はいない。
仮に溺れたのだとしても助けを呼ぶ声は誰も聞いていない。という謎を考察するね。
先ほどの声が聞こえないことと関連する疑惑だね。
「溺れた可能性と言って警察に届け出ているが溺れた姿を見た人はいない」ことに関しては、
泳ぎ初めて対岸に着き戻ってくるNさんを見失ったと報告書に書いていので矛盾はしないかと思う。
助けを呼ぶ声を誰も聞いていない、に関してもこの地底湖は対岸の25メートル先の声はかき消され
のだから、突発的に溺れた際に口に水などが侵入する中で叫ぶ声が聞こえなかったとしても不思議ではないように思うね。
溺れそうになった時に大声は出せない気がします。
この報告書内の記述を見てほしい。
・断続的にその後も「Nくーん!」「早く戻ってこーい!」などと呼び掛けていたが応答はなく、
水音や反響で聞えていないと考えた班員が「おーい」と呼び掛けると、初めて「おーい」との声がNから返ってきた。
・10秒から15秒後に再度「おーい」と呼び掛けると、これにも「おーい」との応答があり、
更に10秒から15秒後に行った3度目の「おーい」との呼び掛けにも、応答が返ってきた。
この3度目の応答は「おーい」と聞き取れるものではなかったが、確かに応答であり、また待機して
せるようなものではなかった。
・更に10秒から15秒後、4度目の「おーい」との呼び掛けを行ったがNからの応答はなかった。
応答が途絶えたため、班員らはここでNに不測の事態が発生したと考え、各自大声で呼び掛けたが
・洞壁や水面にはNのライトの反射は見えず、湖面にも波紋はなかった。
Oが左壁面沿いに5、6メートル泳ぎ出て、死角のない位置から湖面全体を確認したが、Nの姿やライトの光は見えなかった。
実際にどの程度の声を発していたかはわからないけど
最初に応答が途絶えてから水音や反響で聞えていないと考えた班員が「おーい」と呼び掛けるところに注目すると、確実に声を届けるためにかなりの声量だったのではないかと予想される。
泳いでいるNさんからの返答も同じく聞こえるようにそれなりの声量を出していたはずだ。
応答が途絶えた際におぼれたのではないかと予想されるがその際に正常な状態では出せた声を出せなかったことは自然だと思うね。
溺れる姿を確認できなかったのもNさんが他のメンバーから死角にいたのだから見えないはずだ
少し泳がなければ死角のない位置に行けなかったとあるため、
泳がないことに決めて出洞の準備を始めた他のメンバーが監視することができなかったと考えられるね。
結果論になってしまいますが、この時に1人でも死角のない場所から見てあげる人がいれば
このような事故にはなっていなかったのかもしれません。
5,入洞したメンバーがニュースによって人数が変わる謎
次は入洞した際メンバーは5人とされているが4人になったり3人になったりニュースによって人数が変わる、という謎だね
これは当時のニュースを確認できないので調べることはできなかったけどが推測することはできる
まずこの事故当日に入洞したのは5人ですが、この日の前日1月4日に同じチームの他のメンバーが4人で入洞している。
さらに当日は同じチーム5名と4名で分かれた班がゴンボウゾネの穴から本小屋の穴までの通り抜けルートで探検しているね。
このように詳細が複雑なのでニュースを見た人が勘違いした可能性や、正しく報道機関に伝わっておらず人数が変化した能性が考えられるね。
この謎は私もそうだろうなと思いました。
6,4人全員で現場から立ち去り、ロープも撤収している謎
次は溺れた可能性があるにも関わらず残りの4人全員で現場から立ち去り、地底湖から挙げる為に必要なローブなど持って出ている。謎を考察するよ
また報告書を見てみよう。
・救援を要請するために出洞する人員について検討し、Fからは洞内では単独行動をしないのが原則であり、2名を残して2名が出洞し、通報するべきという意見が出た。
・しかしこの時点で、O、K、Sの3人は湖で泳いでいたほか、Fも地底湖に到達する途中の水流部で全身が濡れていたため、長時間この場所に停滞することは低体温症を引き起す危険があった。
Oは2名を残した場合、二次災害の危険性が高いと判断し、全員での出洞を決断した。
・Nを待機していた場所の目立つ岩の上へ「N君へ、ここで待っていてください。救援が来ます」と書いたメモと、保温性の高いサバイバルシートを置いた。
このメモの場所にライト等を点燈設置することはしなかった。
・午後2時50分に出洞を開始し、各ラダーポイントに張ったロープはそのまま残置した。
出洞するまでの間にOとFが通報について検討を行い、警察と消防に通報する必要があるとの結論に達した。
低体温症による二次災害を危惧して全員出洞したんですね。
Fさんは2名を残し2名で出洞し通報という意見を出しており、
仮にFさんの意見を取り入れた場合Nさんが助かっていた可能性も0ではないかもしれない。
しかし4人が出洞したのが5日の15時、5日の23時に警察が入洞し3時間かけて地底湖まで辿り着いているので
翌6日の2時に着いたことになる。この間10時間。
真冬の洞窟の中で全身濡れた状態で10時間助けに来ない状態が続けば本当に2次災害になっていた可能性があるため、このメンバーがとった選択を完全に否定することはできないのではないかと思う。
ライフジャケットはおろか浮き輪すらなかった状況で白濁した湖からNさんを残った2名で捜索することは難しかったように思うね。
想像以上に過酷ですね…。この状況で完全に正しい判断はできなかったと思います。
地底湖から出るのに必要なロープなどを撤去している点は、
報告書には各ラダーポイントに張ったロープはそのまま残置したとある。
ラダーポイントとはロープなどを使用しなければ通れない高低差が激しいポイントのことだ。
そしてこのような記述もある
・徹夜で捜索を行ったが、捜索隊の体力の消耗も激しく、6日午前8時に一旦中断し、7日午前9時から再開することとした。捜索隊が入洞してのち、連絡員1人を神社に残したほかは合宿参加者は全員宿所に戻っていたが、
6日朝の起床後に日咩坂鐘乳穴へ向い、出洞してきた捜索隊からDら3人が状況説明を受けた。
その話から、捜索は水中のみであり支洞部分は行っていないことを知り、
二次災害のおそれの少ないDら3名が捜索を行うことを提案し、警察も了承した。
・3名は午前11時に入洞したが、第二ラダーポイントで残置されていると考えていた補助ロープを発見できず捜索を終了、
その後、現地に駆け付けた高知大学学術探検部OBの1名を加えて、警察に連絡の上午後6時20分に再び入洞、
2人ずつに分かれてそれぞれ支洞と地底湖の捜索を行った。
撤去したわけではなく、発見できなかった?
そうなんだ。同じ探検チームであるDら3人が捜索に入洞した際に第二ラダーポイントで
残置されていると考えていた補助ロープを発見できず捜索を終了とあるね。
この記述から地底湖から出る際に必要なローブなど撤去しているという情報が出回っているのかもしれない。
しかしこの補助ロープはNさんと一緒に入った4人がわざと撤去したのではないかという説がおそらく違うのではないかと私は推測する。
理由は第二ラダーポイントで残置されていると考えていた補助ロープを発見できず捜索を終了したのは
警察が地底湖捜索した後に捜索を試みた「Dら3人だけ」なんだ。
捜索隊は最初の入道の際に一度地底湖へ到達しているということはロープは確実にあったはず。
さらにDら3人がロープを発見できなかった後も捜索隊は地底湖まで行き捜索していることから確実にロープはあったと言える。
Nさん捜索の指揮をとった岡山県警機動隊の警部補は「隊員歴16年の中でも3本の指に入る大変さだった」と語っています
Dら3人も暗く目印が少ない洞内で第2ラダーポイントの補助ロープが発見できないのも仕方ないのかもしれない。
隊員歴16年の中でも3本の指に入る大変さはやばそうですね。
探検サークルのHP上で部長と副部長の名前が事故後削除されている謎
次に探検サークルのHP上で部長と副部長の名前が事故後削除されている。謎を考察するよ。この事故が悪い意味で話題になってしまったのはこの謎が原因なのかもしれないね。
しかし先に示してた入洞したメンバーの情報を見てほしい
| 所属 | 氏名 | 学年(年齢) | 性別 | 洞窟経験 | 日咩坂入洞回数 | 地底湖横断経験 |
| 香川大学ODSC | O | 5回生(24歳) | 女性 | 5年 | 3回 | なし |
| F | 3回生(22歳) | 3年 | なし | |||
| S | 1回生(19歳) | 男性 | 4ヶ月 | 1回 | ||
| 高知大学学術探検部 | N | 3回生(21歳) | 3年 | なし | ||
| 浜松ケイビングクラブ | K | OB(29歳) | 4年 | 4回 | なし | |
実は事故当日に入洞した高知大学学術探検部はNさん1人だけなんだ。
この探検チームは他の大学との合同合宿だったんだ。
探検チームは愛媛大学学術探検部のOB、OG計2名、
高知大学学術探検部のOB1名と現役生3名、
香川大学アウトドアスポーツクラブ(ODSC)の現役生5名、
山口大学洞穴研究会と広島大学探検部のOB各1名、
浜松ケイビングクラブの会員1名の計15名が参加していた。
高知大学学術探検部のOB1名と現役生3名なのでNさんの他に現役生が2名参加していたが、入洞組ではなく通り抜けルート組だったのだと思う。
イメージで高知大学学術探検部内の人間関係などから起きた事件と考えて部長と副部長が関与していたと思ってしまった人がいたのだと思う。
ホームページ上で部長と副部長の名前が事故後削除されていたのは事故がネット上で思わぬ広がり方をしていて恐怖から削除してしまったのか
NさんのSNSが事故後何者かによって投稿記事の中身が削除されていることも同様の理由で、こちらも恐らく部長や副部長がネット上で炎上していることから対策として記事を削除したのだと思う。
どのようにNさんの投稿を削除したかはNさんの親族にお願いした可能性があるね
その記事削除やホームページ上の名前の削除がネット上で逆に怪しまれる材料になってしまったのだけどこれは難しい問題だね。
さらに、調べてもこの当時の部長副部長が高知大学学術探検部の現役生3名にいたのかは確認できなかった。
HP上の名前削除や記事削除の件から参加していたのだろうと思われただけで実際参加していなかった可能性すらあるんだ。
事件と無関係の人がネット上で疑われてたとしたら、可哀想すぎます。
岡山地底湖大学生行方不明事故の考察まとめ
Nさんが発見されていないことから、事故が起った原因は特定されていないが、調査報告書では、「事故者は何らかの原因により、地底湖横断中、帰路において地底湖に沈んだと考えられる」とした上で、
「地底湖を横断中に体力が尽きた」「地底湖横断中に足が攣った」「地底湖横断中にパニックに陥った」
「地底湖横断中に意識を喪失した」「地底湖横断中に死に直結する生理学的な反射を引き起こした」と、考えられる原因を挙げている。
私が考える真相も、足が攣ってパニックになり声もあげれずに沈んでしまって白濁した湖の中で見つけてもらうことができなかったのではないかと思う。
まだ今ほどネットの炎上事件などがない環境で対策を間違えてしまったり、イメージ画像の怖さ、被害者は行方不明のままという色々な要因が重なって都市伝説や闇のように考えられるようになってしまった事故なのかもしれませんね。
今日はここまで。今回は岡山地底湖行方不明事件の謎を考察しました。
まとめると、Nさんは地底湖遊泳中に溺れてしまった、他のメンバーは事件を隠蔽しようとしていない、Nさんの大学の他の部員は地底湖にはきていない。
素晴らしい。その通り。
ここまで見てくださってありがとうございました。よかったらyoutubeチャンネルを登録してくださるととても励みになるのでよろしくお願いします。
では、オツカレサマデシタ。
オツカレサマデシタ